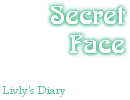鉄はなぜ磁石にくっつくのか。全てのものが磁力を持ちながら、どうして鉄だけがくっつくのか。鉄はなぜ磁石を近づけるとその内部の磁力の向きが揃うのか。どうして内部の磁力が揃うのかっていう説明がないのは"かんたん物理学"だから?
「どうして?」だけではなく「ではその磁力を使ってどんなことができるのだろう」と発展させて考えていくのが大切。
ところで次回予告「台風は、なぜ渦を巻く?」…地学じゃないの?
 磁石のナゾを解く
磁石のナゾを解く
―体内磁石からオーロラまで
中村 弘著:講談社 (1991/01)
微小磁石をもつ細菌がある。地球も巨大磁石。リニアモーター・カーは磁石で疾走し、光通信も磁石抜きでは成り立たない。電気製品のほとんどは磁石のおかげで働いているし、最近では健康にもハイテクにも、大いに役立っている。身の周りには磁石が満ちあふれている。意外や知られていない、磁石のナゾを40項目集め、豊富なビジュアルでやさしく解説。
 磁石のはなし
磁石のはなし
谷腰 欣司 著:日刊工業新聞社 (1996/11)
「磁石とは何か」と聞かれても、鉄を吸い付けるとか、NS極があると説明するだけ。しかし実際は自動車、テレビ、オーディオ、健康器具等、身近な製品に組み込まれている磁石の機能をやさしく解説した本。

図解 磁石と磁気のしくみ
谷腰 欣司 著:日本実業出版社 (2000/01)
磁石と磁気について、「フレミングの右手の法則」「電磁誘導の法則」などの基本はもちろん、身の回りの具体的な製品を例に挙げながら、そのしくみを解説する。雑学的知識も盛りだくさんの入門書。

アメノヒグラシとピグミーが磁石で潰されてる:-p
小さい頃、どうして磁石につくものとつかないものがあるのか
まだ理解が浅かった時にはこうやって「ぐいぐい」って
磁石を押し付けていた記憶があります。
ヤグラは電磁性なのかなぁ。先週の電流も然り。
博士の〆の黒板にマグネットで紙を貼り付けるのってよくやったよね。
あれって紙の方を準備するほうが大変だった。懐かしいなぁ。講師時代。
≪ 続きを隠す










 これは24日のイベントの時に壁に掲示されていました。
あぁ、次回は音なのかぁ…と。専門分野だなぁ、と。
って、自分の専門分野は音楽だけじゃないのがミソです(笑
これは24日のイベントの時に壁に掲示されていました。
あぁ、次回は音なのかぁ…と。専門分野だなぁ、と。
って、自分の専門分野は音楽だけじゃないのがミソです(笑